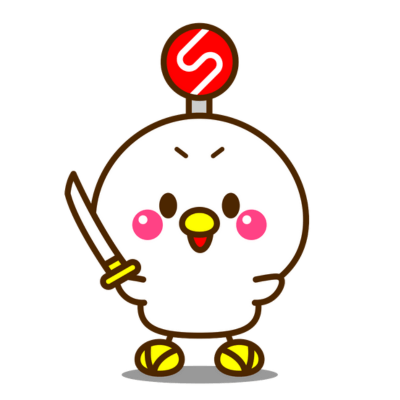今回は、2025年1月19日(日)に行われた2025年度大学入学共通テスト「情報I」について、侍エンジニアの講師であり現役エンジニアでもある永嶋梓インストラクター、株式会社SAMURAI 執行役員CTOの上田悠司、同じく株式会社SAMURAI 新事業開発担当の草郷雅幸がレビューを実施し、テストの内容やポイント、次年度の共通テストを受験する生徒たちに向けて「どのような学習が求められるか」などを徹底解説しました。
- 今回の試験は、データ分析や統計など、AI活用の前提となる知識を問う問題が多かった
- 今後の教育の中で「自分で問題を見つけて解決するスキル」がどのように育まれるかが鍵
- 今まず取り組むべきは、生成AIの情報を自ら獲得し、理解を深めていくこと
今回の座談会登壇者はこちら!

SAMURAIインストラクター/現役エンジニア
永嶋 梓
3年間IoTとPythonを駆使し機械学習を用いた植物工場の制御システム研究に従事。現在は独立し、フリーランスとしてJavaScriptとApexを使用したSalesforceの上流工程設計や業務効率化に取り組む。SAMURAIでは生成AIやMicrosoft製品に関する公開講座の講師も担当。

株式会社SAMURAI 執行役員CTO
上田 悠司
新卒で楽天株式会社に入社。バックエンドエンジニアとして高負荷環境下での開発を担当。その後パーソル株式会社の新規事業開発部でHRTech領域のSaaSに立ち上げ期より参画、事業のMBO後は開発責任者として携わる。2019年4月にSAMURAIに入社。マンツーマン事業の品質向上や学習システムの開発など、エンジニアとして全事業の開発領域に携わる。

株式会社SAMURAI 新事業開発担当
草郷 雅幸
小中高生向け通信教育会社にて、教室事業、EdTech事業、海外事業などを担当。特にEdTech事業では、デジタル端末を使った教育サービスの開発やAIを活用した教材開発、プログラミング教育事業の立ち上げなどに携わる。また、米国にて教育事業会社を設立。SAMURAIでは、変革する社会に対して、学習者のベネフィットを高め、社会に貢献するための新事業の開発を担当。
なお、座談会の様子はYouTubeでもご覧いただけます!
大学入学共通テスト「情報Ⅰ」初年度の実施報告と感想
令和4年度より、新しい高等学校学習指導要領に基づき、高等学校情報科においては共通必履修科目「情報Ⅰ」が新設され、全ての生徒がプログラミングやネットワーク、データベースの基礎等について学習することとなりました。
大学入学共通テスト「情報Ⅰ」とは?
SAMURAI草郷:そもそも「情報Ⅰ」は、
- 情報化社会における基礎的な知識と技能を身につけること
- 情報技術を適切に活用できる人材を育成すること
- 情報社会で必要とされる問題解決能力や情報モラルを養うこと
を目的とした教科です。
その資質・能力を評価・判定するための大学入学共通テスト「情報Ⅰ」は、大きく4つの要素で構成されています。

SAMURAI草郷:1つ目は、「情報社会の問題解決」です。情報技術が人や社会に与える影響、情報モラル、情報技術の役割などを問う内容です。
2つ目は、「コミュニケーションと情報デザイン」です。メディアの特性、コミュニケーション手段、情報デザインの考え方や表現スキルなどを問う内容です。
3つ目は、「コンピュータとプログラミング」についてです。コンピュータの仕組み、アルゴリズム、プログラミング、シミュレーションなどが問われます。
4つ目は、「情報通信ネットワークとデータの活用」です。情報通信ネットワークの設計と構築、データベースの活用方法、データ分析などについて問われます。
大学入学共通テストに「情報Ⅰ」が追加された理由は?
文部科学省が公表した「大学入学共通テストへの『情報Ⅰ』の導入について」資料によると、以下のように書かれています。
IoT・AIの進化やビッグデータ活用などSociety5.0に向けた技術革新や、グローバル化の急速な進展が我々の生活や産業の変革をもたらしている。
こうした社会の変化を踏まえて、高等学校においては、新学習指導要領において、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結びつきの視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を全ての生徒に育む「情報Ⅰ」が必履修科目として設けられた。
また、大学においても、文理問わず、全ての学生が身につけるべき教養教育として、「データ」をもとに事象を適切に捉え、分析・説明できる力を修得するため、「数理・データサイエンス・AI」のモデルカリキュラムが策定されるとともに、その普及を促進するため教育プログラムの認定制度も開始されたところである。
上記のような高等学校教育、大学教育の動向を踏まえると、今後、大学において、情報に関わる資質・能力について、大学教育を受けるために必要な基礎的な能力として捉え、国語、数学、英語等と同様に、大学入学者選抜の過程でその能力を評価・判定していくことも考えられる。
大学入学者選抜の中で、大学入学共通テストは、高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的として、これを利用する大学が共同して実施するものとして位置づけられている。
新しい高等学校学習指導要領の下で学習した生徒が初めて大学受験する令和7年度入学者選抜に合わせて、大学の判断により、大学入学共通テストを利用して、情報に関わる資質・能力を評価・判定することができるよう、大学入学者選抜協議会における協議を経て『情報Ⅰ』を導入することが決定された。
つまり、グローバル化が進む社会の変化を踏まえ、全ての生徒に情報技術を活用する力を身に付けさせ、また大学教育を受けるために必要な基礎的な能力として、情報に関わる資質・能力を評価・判定することができるよう、大学入学共通テストに「情報Ⅰ」を導入することを決定したということです。
実際の問題を見て感じること
SAMURAI草郷:お二人は実際の問題をご覧になって、どのように感じられましたか?
SAMURAI上田:まさに「情報」だな、という印象を受けました。それが何を意味しているかというと、情報化社会の中で「いかにシステムを理解しながら生きているか」を総合的に問われていると思います。
そこには「これからの情報化社会をどう生きるか、どう生き延びていくか」という部分が意味として込められているように感じました。
永嶋インストラクター:基礎的なITスキルを幅広く学ぶカリキュラムの中で、プログラミングやデータ活用、情報セキュリティ、情報ネットワークなど、重要なトピックが網羅されていて、非常に幅広い知識が問われる内容だったと思います。
プログラミングももちろん大事ではありますが、データ分析や統計など、AI活用の前提となる知識を問う問題が多かった点は印象的です。
SAMURAI上田:第3問はプログラミングの問題でしたね。基礎的なプログラミング力や考え方が求められている内容だったかと思います。自分の時には大学で学ぶような内容でしたので、「今は高校生で学ぶのだな」と、ある意味でジェネレーションギャップを感じました。
永嶋インストラクター:第3問の内容は、基本情報技術者試験の中にも含まれるようなアルゴリズム的な内容だったかと思います。逆に第3問以外の部分については、いかに情報を活用していくのかに重きを置いた内容だったと感じます。
面白いなと思ったのは「レシート」の問題(第2問)ですね。
日常生活の中で「どう情報を活用するのか」を問う問題で、受験生にもイメージしやすかったのではないかと思います。実際のデータ活用の現場においても議論されているような内容なので、良い問題だったと思います。
SAMURAI上田:私も同じくレシートの問題を興味深く見ていました。最終的にユーザーに見えるアウトプット(今回の場合はレシート)の裏側に、どんなデータがあって、どんな分析がされているのかにも言及されているので、システムエンジニアが日常で見る景色に通ずる内容だったと感じます。


大学入学共通テスト「情報Ⅰ」が育むITスキルとは
SAMURAI草郷:「情報Ⅰ」を学習することでどのようなスキルを身につけることができるのか、また実社会においてどのように活かしていけるのかについて、現役エンジニアのご意見を伺いたいです。
永嶋インストラクター:「情報Ⅰ」は、単なるスキル習得だけではなく、情報を活用して問題解決する能力を身につけることが大事になります。データの活用、分析から課題を見つけることやITを使って解決することは社会の中でも使われるスキルになるので、学ぶことは意味のあることだと思います。例えば現場で困っていることを限られたリソースの中で解決したり、成果を最大限出すことが求められていますし、それをプログラミングを使って実現しています。
SAMURAI草郷:そうなると、「情報Ⅰ」だけでなく社会も含めて他の領域の学びと結びつけていくことで、より「情報Ⅰ」の学びが深くなるとともに「課題解決」という実践に繋がっていくかもしれませんね。
SAMURAI草郷:高校生が「情報Ⅰ」の学びを実際に社会で活かす機会はありそうですか?
SAMURAI上田:問題を見ると、知識を確認するというよりは、データを見てどう課題解決していくのか、システム全体を見て裏側でどのようなシステムが動いているのかなど、培ったスキルを実社会でいかに活用するかの基礎的な内容をしっかり含んでいます。つまり、知識を使って社会の課題を解決するスキルが身につくことを重要視しているので、そこを伸ばすのがいいと思います。
プログラミングスキルがあれば、自分でプログラムを作成できるので社会に活かせるようになりますが、データ分析については、実際のデータを扱うことになり、現実的な世界の話になるので、社会に出ないと経験するのが難しいかもしれません。
「情報Ⅰ」で身に付けたスキルを社会で活かすためにさらに必要なこと
永嶋インストラクター:情報Ⅰで学ぶ擬似言語に近いPythonやJavaScriptは比較的学習しやすい言語なので、情報Ⅰを学んだのちに触れるには良い言語だと思います。Pythonであれば、AIや機械学習でも使えますし、アプリなどを作ることもできるので、さらに続けて学んでいくのがいいでしょう。
SAMURAI上田:実際に自分で手を動かして理解を深めていくような機会があると、より実践に繋がっていくのではないでしょうか。自分でプログラムを作ってみるのはいい経験になると思います。日常生活の中や部活など小さいことでも学んだことを現実世界に当てはめて、試行錯誤することで見えてくる課題もあると思います。
「協働」で何かを推進することの大切さ
SAMURAI上田:開発の現場ではチームでの開発が主流です。自分一人ですべてを開発するという機会は稀ですし、誰かと一緒に仕事をするのは普通のことだと思います。仕事以外の身の回りのことでも自分一人でできることには限界があるので、役割分担することで、自分一人ではできなかったことができるようになります。だから、チームで開発することは楽しいですし、社会に出ても役に立つことだと思います。
永嶋インストラクター:プログラミングスキルだけでなく、協働の中ではコミュニケーション能力が重要です。上田さんのおっしゃる通りチーム開発の場面がほとんどですので、プログラミングスキルだけでなく協調性や言語化するスキルも併せて身につけてもらいたいと思いますね。
SAMURAI草郷:やはり社会という枠で見ると、「情報Ⅰ」の知識やプログラミングスキルだけではなく、協調性やコミュニケーション能力も身につけていくことが大切ですよね。
未来に向けて、「情報Ⅰ」の次に取り組むべきこと
SAMURAI草郷:未来に向けて、「情報Ⅰ」の次に取り組むべきことについて、どのように考えていますか?特に、生成AIなどが社会で一般化する中で、どのような知識や能力を養うのかをお聞きかせください。
永嶋インストラクター:生成AIや機械学習の基礎を理解していて損することは絶対にありませんし、プログラミングの基礎を幅広く学んでおくことで「AIに振り回されない」で、「適切にAIを活用できる」状態になれると思います。そのためには、色々な言語を幅広く知っておくことが大切です。AIからのアウトプットをしっかり判断して、アプリなどを作っていくことが必要です。
SAMURAI上田:昨今、生成AIの活用が活発になっており、それによってコードを書くことへのハードルが下がってきているように感じます。自分も1人のエンジニアとして「プログラミングを書く」という仕事がどのくらい残るのか分かりませんが、何かを実現する手段としてプログラミングは残るし、個々人がそれを使いこなせる世界がくると思いますので、生成AIの情報を自ら獲得し、理解を深めていくことが今まず取り組むべきことかなと考えています。生成AIの波に乗って、自分でプログラミングを動かしてみて、自分でその波をキャッチして、自分で経験してほしいと思います。
SAMURAI草郷:生成AIを使いこなせるようになることが大切だということですね。人間中心でどのように活用するのかということがこれから課題になっていくと思いますが、まずは基本を身に付けつつ、活用方法を学び、活用して慣れることですね。
まとめ
永嶋インストラクター:もし、高校の時に情報Ⅰを学んでいたら、プログラミングでアプリやプロダクトなどを作ってみて、現実社会の問題について、使う側ではなくて作る側の目線でクリエーターとして考えるとおもしろいと思って、取り組んでいるのではないかと思います。
エンジニアは新しい技術が出ると、新しいおもちゃを得たと思って遊んでいるような人たちですが、ぜひ楽しみながら勉強したり、新しいものを作ったりしてほしいと思います。
SAMURAI上田:紙の上だけではなく、実際にプログラムを書いて手を動かしてみると、色々な課題が見えてきて、より解像度を高くして情報と向き合えるので、ぜひ手を動かしてみるのがいいでしょう。また、レシートの問題の例にもあるように、現実社会の中で、システムがどのように動いているのかを想像するきっかけになったかなと思いますので、日常的にそういったことを想像する機会を作ることは、エンジニアを目指している方には、特に仕事に活かせるところなので、情報Ⅰで学んだことを活かしてほしいです。
SAMURAI草郷:本日は、初めて実施された共通テストの「情報Ⅰ」について、現役エンジニアの方も含めて、実践的な面からの成果と課題、また今後のIT教育について多くの示唆をいただきました。特に、技術的スキルだけでなく、知識とスキルを統合し、実社会で活用する能力を育む教育の必要性が明らかになりました。
情報Ⅰをきっかけに、PythonやJavaScriptなどの言語を学ぶことによって、知識やスキルを活かす機会ができると思うので、継続して学ぶ機会を作ってほしいと思います。
本日はありがとうございました!