この記事では必要なスキルや活用法も交え、生成AIを使いこなす人材になる学習手順を解説します。
生成AIを使いこなすにはどうしたらいいんだろう?
使いこなすコツなどはあるのかな?
ChatGPTといった生成AIを利用し始めたものの、いまひとつ使いこなせていないモヤモヤした感覚の人は多いのではなないでしょうか、
生成AIを使いこなすには、基本的なことから正しく理解を深めていくことが大切です。
そこでこの記事では必要なスキルや活用例も交え、生成AIを使いこなすコツを紹介します。この記事を読めば、初心者の人も生成AIを使いこなすイメージが湧きますよ。
- 生成AIの活用でコスト以上の価値を得よう
- 生成AIを使いこなすにはスキル習得が必須
- 本や講座、スクールでの学習がおすすめ
「生成AIを使いこなすスキルは欲しいけど、自力で身につけられる自信がない…」
そんな不安を抱えている人は、ぜひ一度「侍エンジニア」をお試しください。
侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポート。AI開発からChatGPTといった生成AIの活用スキルまでを一貫して身につけられます。
これまで4万5,000名以上の受講生を指導してきた侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくAIを使いこなせるようになりますよ。
生成AIを使いこなす=コスト以上の価値を得る
最初に「生成AIを使いこなす」の意味を明確にしておきましょう。「生成AIを使いこなす」とは、生成AIを活用することで、自分がかけたコスト(時間・労力・リスクなど)以上の価値を得ることを指します。
「生成AIは無料プランならノーコスト」と思われがちですが、それは正しくありません。生成AIとのやり取りに費やす時間も立派なコストです。また「誤情報に惑わされる」といったリスクも潜在的なコストといえます。
これらを総合して”コスト”と捉え、それ以上の価値を引き出すのが「生成AIを使いこなす」です。逆に、生成AIをうまく使いこなせなければ、次のような問題に直面しかねません。
- 期待した回答が得られず成果物の品質が低下する
- 自分で作業したほうが早く、かえって非効率になる
- 想定外のリスクが表面化し、本来の目的に集中できなくなる
こうした事態を避け、本当の意味で生成AIを使いこなすには、次のポイントを押さえておく必要があります。
- 生成AIが役立つ具体的なシーンや指示の出し方
- 生成AIから求める回答を引き出せる指示のコツやテクニック
- 生成AIの活用に必要なスキルや学習方法
これらを理解・実践し、生成AIを使いこなせる人材=コスト以上の価値を生み出せる人材を目指しましょう。
生成AIを使いこなすための前提知識

生成AIを使いこなすには「そもそも生成AIとは何なのか」といった前提知識の理解が不可欠です。
そこでここからは次のトピック別に、生成AIを使いこなす前提知識を紹介します。
そもそも生成AIとは
生成AIとは、テキストや画像、音声といったコンテンツを生成できるAI(人工知能)のことです。「プロンプト」と呼ばれる指示文章を与えることで、AIが指示に沿ったコンテンツを生成してくれます。
生成AIの特徴は、人間の言葉から内容や文脈を把握する「自然言語処理」を活用している点。自然言語処理によって指示内容や文脈を高精度に把握できるため、プロンプト次第でさまざまな使い方が可能です。
生成AIの概要をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
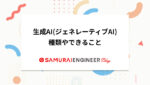
生成AIの種類
生成AIにはいくつかの種類があり、それぞれ生成できるコンテンツが異なります。代表的なものを下表にまとめました。
各生成AIの活用価値は業種や目的によって異なりますが、最も汎用性が高いのはテキスト生成AIです。この記事では、このテキスト生成AIにフォーカスして解説していきます。
生成AIを使いこなすのに必要な4つのスキル

生成AIを使うために特別な資格は必要ありません。しかし、生成AIを使いこなすには相応のスキルが求められます。
そこでここからは、生成AIを使いこなすのに必要なスキルを、4つにまとめて紹介します。
生成AIの基礎知識
生成AIを使いこなすための第一歩は、できることや仕組み、性質といった基礎知識を押さえることです。生成AIの基礎知識を持たずに利用すると、次のような問題に直面する恐れがあります。
- 生成AIにできないことを無理に指示し、時間を浪費する
- 生成AIの設定や使い方を誤り、重要な情報が漏えいする
- 生成AIの回答を過信し、誤情報をそのまま使ってしまう
生成AIはあくまでソフトウェアであり、人間の部下と同じ感覚で使うと思わぬリスクが生じます。生成AIの使い方を誤らないよう、最初に基本的な知識は身につけておきましょう。
プロンプトエンジニアリングのスキル
生成AIを使いこなすには「プロンプトエンジニアリング」のスキルが欠かせません。プロンプトエンジニアリングとは、生成AIに与えるプロンプトの内容を設計・最適化し、理想的な回答を引き出す作業のことです。
プロンプトエンジニアリングのスキルがあると、生成AIに「やりたいこと」を正しく伝達でき、回答の品質や精度を向上できます。生成AIとのやり取りを効率化するうえでも重要となるスキルです。
プロンプトエンジニアリングについてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
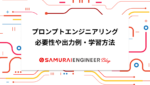
情報リテラシー
生成AIを使ううえで「情報リテラシー」が不可欠です。情報リテラシーとは、情報を目的に合わせて正しく活用できるスキルのこと。IT社会に必須のスキルですが、生成AIの活用時には特に重要となります。
生成AIはWeb上の膨大な情報から学習し、その知識にもとづいて回答します。しかし、それらの中には誤った情報も少なくありません。情報リテラシーは、情報の信頼性を見極め、必要なものを取捨選択するために必須です。
情報リテラシーがあれば、生成AIの情報を鵜吞みにせず、価値ある情報だけを活用できるでしょう。
論理的思考力
生成AIを使いこなすには「論理的思考力」が求められます。論理的思考力とは、論理に沿って矛盾なく物事を考えるスキルのことです。汎用性が高いスキルですが、生成AIとのやり取りでも大きな効果を発揮します。
たとえば指示があいまいだったり、矛盾を含んでいたりすると、生成AIから期待する回答は得られません。生成AIから理想的な回答を得るためには、論理的に整理されたプロンプトを考えることが求められます。
論理的思考力があれば、複雑な問題でも「どう指示すれば最短ルートで答えを導けるか」を考え、効率よく問題を解決できるでしょう。
生成AIを使いこなすおすすめの活用法6選
なかには、生成AIを使いこなすイメージが湧いていない人もいますよね。
そこでここからは次の用途別に、生成を使いこなすおすすめの活用法を紹介します。
文章・資料の作成
テキスト生成AIを活用することで、メールやレポートの文章、プレゼンやマニュアルなどの資料を効率よく作成できます。たとえば、次のプロンプトを生成AIに送信することで、簡単にメール本文のたたき台を作成可能です。
| 先日打ち合わせをした〇〇株式会社の△△様に、感謝の気持ちを伝えるお礼メールの本文を作ってください。打ち合わせで得た学びや、今後の協力への期待も少し盛り込みたいです。 |
ChatGPTにプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。お礼メールの本文を作成してくれました。細かい部分だけ手直しすれば、短時間でメール本文を完成できそうです。

文章や資料の作成はテキスト生成AIの得意分野であり、あらゆる業種で活用できるでしょう。
図表・グラフの作成
テキスト生成AIには、データをもとに図表やグラフを作成できるサービスもあります。たとえば、次のプロンプトを「Claude」などの生成AIに送信することで、売上データからグラフを作成可能です。
| 以下の売上データをもとに、四半期ごとの売上推移を棒グラフで作成してください。 ## 売上データ 2024年1月:100万円 2024年4月:120万円 2024年7月:150万円 2024年10月:130万円 ## 前提条件 プレゼン資料に使うため、グラフは視認性を重視したデザインでお願いします。 |
Claudeにプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。売上データから棒グラフを作成してくれました。

データを図表やグラフで整理・可視化したい場合には、生成AIを用いるのが便利です。ただし、サービスによっては図表やグラフの作成に対応していない場合があるため注意しましょう。
文章の要約・翻訳
テキスト生成AIは、長い文章を要約したり、外国語の文章を翻訳したりすることも可能です。たとえば、次のプロンプトを生成AIに送信することで、与えた英文を日本語に翻訳できます。
| 下記の英文を、ですます調で日本語に翻訳してください。 While the proposal lacks specific implementation details, its underlying framework presents a compelling vision for future development. Further clarification would significantly enhance its practical value. |
ChatGPTにプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。英文を日本語に翻訳してくれました。

長文や外国語の内容を素早く把握したいときには、このように生成AIが役立ちます。
調査・情報収集
Web上のデータから知識を得ているテキスト生成AIは、さまざまな調査や情報収集にも活用できます。たとえば、次のプロンプトを生成AIに送信することで「Web上でおすすめされている生成AI」を調査可能です。
| おすすめ生成AIを紹介しているサイトを参照し、下記の各種類に対して「多くおすすめされている生成AI」を上位3サービスまで調査してください。 – テキスト生成AI- 画像生成AI- 音声生成AI- 動画生成AI |
普通に生成AIへ質問することも可能ですが、最近では「Gemini Deep Research」など、調査に特化した機能もあります。GeminiのDeep Research機能を用いてプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。
Web上でおすすめされている生成AIを調査し、その結果を7,000文字ほどのレポートとして出力してくれました。

もちろん、人間による調査内容のチェックは必要です。しかし、大量のWebサイトを渡り歩くよりも格段に調査や情報収集を効率化できるでしょう。
アイデア出し
テキスト生成AIは、さまざまなビジネスシーンにおけるアイデア出しにも役立ちます。たとえば、次のプロンプトを生成AIに送信することで、新規事業のアイデア出しが可能です。
| 下記の条件に合う新規事業アイデアを3つ提案してください。 ## ターゲット 20代後半〜30代前半の働く女性(都市部在住、仕事と私生活を両立したい層) ## 技術トレンド – サステナビリティ – AIによるパーソナライズ ## 出力 – アイデア名(10文字以内) – 概要(2〜3行) – ターゲットの課題と解決方法 – 収益化の可能性 |
ChatGPTにプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。新規事業アイデアを3つ提案してくれました。

生成AIは既存のデータをもとに回答するため、ゼロから画期的なアイデアを提案することは難しいです。しかし、既存の要素を組み合わせたアイデアは提案できます。アイデアを効率よく出したいときに活用しましょう。
思考の整理
「何から手をつければよいかわからない」「頭の中がごちゃごちゃしている」という場合も、テキスト生成AIは便利です。たとえば、次のプロンプトを生成AIに送信することで、商品企画の思考整理を手伝ってくれます。
| 新しい「20代女性向けの美容家電」の商品企画を考えたいのですが、まだ方向性が定まっておらず、何から考え始めるべきか整理したいです。下記の条件を踏まえて、アイデア出しのヒントになるようなキーワードや、考えを広げるための切り口を、マインドマップや箇条書きなどでまとめてください。 ターゲット:SNSで美容情報を積極的に収集している20代女性 技術面:既存技術の応用も、新しいアイデアの提案も歓迎 予算:できるだけ抑えたいが、価値があれば多少のコスト増はOK 競合:大手ブランドはあるが、まだ詳しく比較できていない状態 思考を広げるための方向性、重要度の整理軸、優先的に考えるべき視点なども盛り込んでもらえると助かります。 |
Claudeにプロンプトを送信したときの回答例は次のとおりです。マインドマップを交え、考えるべき視点などを整理してくれました。

このように、生成AIは明確なアウトプットだけでなく、考えを言語化・構造化するプロセスでも役立ちます。
生成AIを使いこなす4つのコツ

生成AIは、コツを押さえて活用することで、回答の精度アップや時間短縮につながります。生成AIを使いこなすためのコツは次の4つです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。なお次の記事では、生成AIから理想的な回答を引き出すコツを紹介しているので、あわせて参考にしてください。
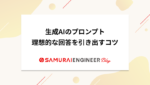
コツ1:明確で具体的な指示を出す
生成AIから期待どおりの回答を得るためには、明確で具体的な指示を出すことが大切です。つまり、生成AIが迷わず処理できるように、十分な情報をプロンプトに盛り込みましょう。
たとえば、生成AIにリストの内容をチェックしてもらいたい場合、次のような指示の方法はNGです。何をもって「問題がない」といえるのかがあいまいなため、生成AIが正しく処理できない場合があります。
| 下記のリストに問題がないかチェックしてください。 北海道 青森県 東京都 横浜市 神奈川県 福岡県 |
いっぽう、次のようにチェックの基準を具体的に示せば、生成AIはより正確に対応できます。
| 下記のリストに都道府県以外のデータが含まれていないかチェックしてください。 北海道 青森県 東京都 横浜市 神奈川県 福岡県 |
あいまいな指示では生成AIが意図をくみ取りきれず、本来の意図とは異なる出力になりがちです。明確で具体的な指示を出し、回答の精度を向上しましょう。
コツ2:フィードバックを繰り返す
一度で完璧なアウトプットを求めるよりも、少しずつフィードバックを与えて改良していくほうが効果的です。生成AIは、回答に対する問題や改善点を指摘すると、より質の高いアウトプットを導き出そうとします。
たとえば「この部分をもっと短くしてください」といったフィードバックを与えることで、生成AIは自分の意図に沿った形で文章を再構成してくれます。
こうしたやりとりを繰り返すうちに、生成AIのアウトプットが自分の求める内容に近づいていくのです。段階的に調整していくことで、方向性を見失わずに作業を進めやすくなり、結果として時間短縮につながるでしょう。
コツ3:複数の生成AIツールを組み合わせる
複数の生成AIツールを組み合わせるのが効果的です。生成AIによって得意分野やできることは異なります。それぞれの長所を組み合わせることで作業の幅が広がり、作業効率も高まるでしょう。
たとえばテキスト生成AIで文章を整え、その内容を画像生成AIで視覚化すると、より魅力的で伝わりやすい資料を作成できます。各生成AIツールが持つ強みを組み合わせると、個々では実現できない成果を得られるのです。
コツ4:プロンプトのテクニックを知る
生成AIに与えるプロンプトのテクニックを知ることで、回答の精度アップや時間短縮を図れます。代表的なテクニックを3つピックアップし、下表にまとめました。
| テクニック | 概要 |
|---|---|
| プロンプトチェイニング | 複雑な課題を細かいタスクに分割し、段階的にプロンプトを与えて解決していく手法 |
| フューショットプロンプティング | いくつかの具体例を示し、生成AIに意図や出力パターンを理解させる手法 |
| CoT(Chain of Thought)プロンプティング | 思考の道筋を示し、生成AIに論理的な手順で課題を解決させる手法 |
こうしたテクニックを知っているかどうかで、生成AIのアウトプットや作業効率は大きく変わってきます。ほかにも多数のテクニックが存在するため、生成AIに関する知識を継続的に学んでいくことが大切です。
生成AIを使いこなす人材になる学習法

生成AIを使いこなす人材になるためには、必要な知識やスキルを身につけるための学習が欠かせません。
ここからは、生成AIを使いこなす人材になるための学習法を、3つにまとめて紹介します。
本で知識を身につける
生成AIを学べる参考書や入門書は数多く出版されています。必要な知識が体系的にまとめられた本は、1冊でしっかり生成AIの知識を吸収できるのがメリットです。
ここでは、生成AIの学習におすすめの本を2冊紹介します。
生成AIの基本や使い方をわかりやすく紹介している1冊です。マンガや図解が充実しているため、IT初心者の人でもスムーズに読み進められるでしょう。
なお、生成AIの学習におすすめの本をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

オンライン講座で学ぶ
「パソコンを使って効率よく学びたい」という人にはオンライン講座がおすすめです。パソコンとインターネット環境さえあれば、自宅で好きなときに生成AIを学べます。
さまざまなオンライン講座がありますが、特におすすめは「侍テラコヤ」です。人気の言語を幅広く学べるプログラミング学習サービスですが、生成AIの基礎を学べるオンライン講座も提供しています。

150種類以上の教材で学べる侍テラコヤでは
- 回答率100%の「Q&A掲示板」
- 勉強の進捗や成果を記録できる「学習ログ」
- 実践的なスキルを身につけられる「課題機能」
- 現役エンジニアとのマンツーマンレッスン
といったサポート体制を整えているため、挫折なくスムーズにスキルを習得可能です。入会金不要・いつでも退会OKに加え「無料会員登録」でお試し利用ができるため、後悔する心配もありません。
コスパよく効率的にスキルを習得したい人は、ぜひ侍テラコヤをお試しください。
なお、生成AIを学べるほかのオンライン講座も知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

スクールに通う
確実性や効率性を重視する人には、スクールに通うのがおすすめです。信頼できる講師から丁寧に教えてもらえるスクールは、独学よりも挫折しにくく、効率よくスキルを習得できます。
昨今では、多くのプログラミングスクールが生成AIを学べるコースを提供しています。こうしたコースを受講すれば、学習の途中でつまずいても講師に相談できるため、挫折しにくいのが大きなメリットです。
なお次の記事では、生成AIを学べるプログラミングスクールを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

挫折なく生成AIを使いこなすには
生成AIを使いこなして業務を効率化したい人は多いでしょう。しかし、独学では時間がかかるうえに挫折しやすいため、このまま独学で進めるべきなのか不安な人も多いですよね。
挫折なく短期間で生成AIの活用スキルを身につけたい人には、侍エンジニアの「業務改善AI活用コース」がおすすめです。累計指導実績45,000名以上のプログラミングスクールによる学習コースです。

このコースでは、ChatGPTを用いたプロンプトエンジニアリングに加え、人気のプログラミング言語「Python」のスキルも学べます。生成AIとプログラミングを掛け合わせ、さらなる業務効率化を図れます。
「短期間で生成AIを使いこなせるようになりたい」「プログラミングスキルも身につけたい」といった人は、ぜひ無料カウンセリングでご相談ください。
まとめ
この記事では「生成AIを使いこなしたい」という人向けに、次の6点についてお伝えしました。
生成AIの有効活用は、業務の効率化だけでなく、新しい価値を生み出せる可能性も秘めています。しかし、生成AIを使いこなすには、必要な知識やスキルを身につけるための学習が欠かせません。
今回の内容を参考に、ぜひ生成AIを使いこなせる人材を目指してみてください。独学に不安を抱えている場合は、スクールを利用するのも1つの手です。
本記事の解説内容に関する補足事項
本記事はプログラミングやWebデザインなど、100種類以上の教材を制作・提供する「侍テラコヤ」、4万5,000名以上の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIが制作しています。
また、当メディア「侍エンジニアブログ」を運営する株式会社SAMURAIは「DX認定取得事業者」に、提供コースは「教育訓練給付制度の指定講座」に選定されており、プログラミングを中心としたITに関する正確な情報提供に努めております。
参考:SAMURAIが「DX認定取得事業者」に選定されました
記事制作の詳しい流れは「SAMURAI ENGINEER Blogのコンテンツ制作フロー」をご確認ください。
この記事の監修者

フルスタックエンジニア
音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。











